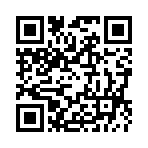フォーサイスから学ぶジャーナリズム
2017/06/18
アガサ・クリスティはじめ推理小説作家が英国に多いのは、ジャーナリズムが早く発達したからだと、日経文化面で読んだ。私が好きなピーター・ラヴゼイ、ロバート・ゴダード、フレデリック・フォーサイスも英国だ。そのフォーサイスは昨年末、自伝とも言える「アウトサイダー」を出版した。最近読んだ本の中では「蜜蜂と遠雷」(恩田陸)と並ぶほど面白い。15歳で大学進学資格試験に合格、19歳でパイロット資格を得、5カ国語を使って世界を股にかける快男児の話は痛快です。
一方で、「ジャッカルの日」を書いて作家になる前、地方紙イースタン・デイリー・プレスの記者、ロイター通信の特派員、BBC放送局の記者を勤めており、ジャーナリスト魂を感じさせるくだりも少なくない。76歳の大先輩の言葉を、若い記者たちにも知ってもらいたい。さわりを転載します。
「(ジャーナリストに必要不可欠な資質は)あくなき好奇心と徹底的な懐疑的態度だ。何かの理由など別に知りたくないというジャーナリストや、人の話をなんでも鵜呑みにするジャーナリストがいるとしたら、それは無能なジャーナリストだ」(11㌻)
「ジャーナリストは絶対に支配階層(エスタブリッシュメント)の一員になるべきでない。誘惑がどれほど強くてもだ。われわれの仕事は権力を監視することであり、そこに加わるべきでない」(同)
「けっして当事者の仲間になってはいけない。アウトサイダーでいなければならないのだ」(12㌻)
「全国紙や通信社の記者は読者と顔を合わせない。だが地方紙では、窓の外に読者たちがいる。社屋に入ってきて、記事に誤りがあると抗議したりする。だから要求される水準が高いのだ」(108㌻)
「報道機関の使命はエスタブリッシュメントに釈明させることにある。絶対にエスタブリッシュメントの一部になってはいけない」(172㌻)
「外国特派員が肝に銘じておかなければならない鉄則がある。外務省の言うことを鵜呑みにするな、現地に長年すんでいる人に話を聞きに行け、という鉄則だ」(188㌻)
「一読者としてのわたしは不快なほどのうるさ型だ。ほかの作家の作品を読んでいると、どうしてもこう考えてしまうのである。この人は本当に現地を見たのだろうかと。(中略)どんな場所も、話しに聞くのと実際に見るのとでは大違いということがある。(中略)自分で行くのが不可能なら、次善の策として、その場所にいたことのある人から話を聞くべきだ」(360㌻)

一方で、「ジャッカルの日」を書いて作家になる前、地方紙イースタン・デイリー・プレスの記者、ロイター通信の特派員、BBC放送局の記者を勤めており、ジャーナリスト魂を感じさせるくだりも少なくない。76歳の大先輩の言葉を、若い記者たちにも知ってもらいたい。さわりを転載します。
「(ジャーナリストに必要不可欠な資質は)あくなき好奇心と徹底的な懐疑的態度だ。何かの理由など別に知りたくないというジャーナリストや、人の話をなんでも鵜呑みにするジャーナリストがいるとしたら、それは無能なジャーナリストだ」(11㌻)
「ジャーナリストは絶対に支配階層(エスタブリッシュメント)の一員になるべきでない。誘惑がどれほど強くてもだ。われわれの仕事は権力を監視することであり、そこに加わるべきでない」(同)
「けっして当事者の仲間になってはいけない。アウトサイダーでいなければならないのだ」(12㌻)
「全国紙や通信社の記者は読者と顔を合わせない。だが地方紙では、窓の外に読者たちがいる。社屋に入ってきて、記事に誤りがあると抗議したりする。だから要求される水準が高いのだ」(108㌻)
「報道機関の使命はエスタブリッシュメントに釈明させることにある。絶対にエスタブリッシュメントの一部になってはいけない」(172㌻)
「外国特派員が肝に銘じておかなければならない鉄則がある。外務省の言うことを鵜呑みにするな、現地に長年すんでいる人に話を聞きに行け、という鉄則だ」(188㌻)
「一読者としてのわたしは不快なほどのうるさ型だ。ほかの作家の作品を読んでいると、どうしてもこう考えてしまうのである。この人は本当に現地を見たのだろうかと。(中略)どんな場所も、話しに聞くのと実際に見るのとでは大違いということがある。(中略)自分で行くのが不可能なら、次善の策として、その場所にいたことのある人から話を聞くべきだ」(360㌻)