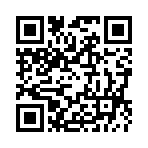2017/06/26
ドゴール仏大統領を狙う暗殺犯と老刑事の攻防を描いた小説「ジャッカルの日」の作者、フレデリック・フォーサイスが、自らの人生を綴った「アウトサイダー」。昨年末KADOKAWAから邦訳が出版された。作家になる前、英国の地方紙イースタン・デイリー・プレスやロイター通信特派員、英BBC放送を経てフリーの記者もしている。
「ジャーナリストは絶対にエスタブリッシュメント(支配階層)の一員になるべきではない」「当事者の仲間になってはいけない。アウトサイダーでいなければならない」と、「はじめに」にある。今年79歳になる先輩ジャーナリストからの忠告の書とも読むことが出来る。
とはいえ、小説同様、軽妙な語り口で痛快だ。17歳で英国空軍に入隊、19歳でパイロット記章を手にし、5カ国語を流暢に操って取材、など快男児のエピソードは読みだしたら止まらない。楽しくページをめくっている時、痛快ではない、記者と当事者をめぐる事件が霞が関で起きた。
4月4日、今村雅弘復興相は記者会見で、東京電力福島第1原発事故に伴う自主避難者への対応を巡り、国の責任を質問したフリーの記者に「出ていきなさい。もう2度と来ないでください」「うるさい」と述べた。
この会見の詳報を読むと、記者への暴言の前に、自主避難者は「本人の判断」「本人の責任」であって、不服なら「裁判でも何でもやれば良い」と、被災者の気持ちに立って考えれば、冷たい発言を復興担当なのにしている。こちらがニュースだった。
しかし、5日の紙面は、共同通信原稿を使った加盟各社と毎日、日経、産経は、記者に対する暴言のみを報道した。読売は、一切記事にしなかった。
一方で朝日は「本人の責任」と述べたことをニュースにし、河北新報も独自の記事で自己責任を見出しに取った。
野党の批判もあり、共同通信は5日、復興相の言動が波紋を広げている、との大型解説記事を会見詳報も付けて流した。東京葛飾区に住む自主避難者の「大臣は汚染の状況を本当に知っているのか」など怒りの談話、福島県が3月末で打ち切った住宅無償提供の対象者が1万524世帯(昨年10月末時点)もいること、復興庁幹部にも「『本人の責任』という発言は、きつい言い方だった」との見解があることに触れた。
6日朝刊で加盟各紙が盛大に使った。地元の福島民友はじめ、秋田魁、中国などが2面などで、新潟日報が第2社会面、京都が社会面で、トップで扱い、東京は、霞ヶ関で開かれた、発言に抗議する集会を1面頭で使い共同記事のさわりを付けた。
信毎は共同記事を3面頭にするとともに、長野県内に自主避難している福島県民を取材し「国は早く避難者を福島に戻し、事故の幕引きを図りたいのだろう。見捨てられるのは悔しい」などの声を3段見出しで付けた。
朝日も第2社会面トップで、「切り捨てたい国の本音」と自主避難者の声をまとめた。
朝日、毎日、北海道、中日、信毎などが社説でも問題にした。復興相は6日、発言を事実上撤回、陳謝した。8日福島を視察した安倍首相が「私からもお詫びしたい」と発言、福島民友、福島民報が2面で大きく取り上げた。
気になるのは、新聞や放送の記者たちが、復興相の「2度と来るな」の発言に、後でどう対応したかだが、紙面では分からない。フリーの記者であっても、記者クラブがあれば抗議すべきところだ。質問内容次第で、記者が閉め出されることになれば、いずれは新聞、放送記者も自由に質問できなくなるからだ。
4日の会見を、かなり細かく記事にしている日本新聞協会の11日付「新聞協会報」によると「復興庁は記者クラブがなく、会見は庁側が運営する」という。なおさら、歯止めが必要で、そうでないと、官庁が気に入る記者のみの会見となり、国民の目がふさがれるのに等しい。
現場で解決できなければ、同協会編集委員会にまで持ち上げる手もある。
一連の報道で、違和感がしたのは、産経の7日5面。復興相が衆院東日本復興特別委で謝罪した記事のわき、「政論」という署名記事だ。「非生産的“逆上狙い”の挑発質問」と3段見出し。暴言のきっかけになった質問は、フリーの記者のたたみかける質問で復興相が感情的になり、暴言につながったとし、「まさに術中にはまったわけだ」と、暴言を引き出す狙いで質問が行われたかのように記述。記者のツイッターまで調べ「安倍晋三政権に批判的な姿勢が目立つ」とし、「『ためにする質疑』は生産的ではない」と結んでいる。
記者会見を生産的か非生産的か、で考えること自体、おかしいが、この筆者が自分は安倍政権にどういう姿勢なのかも書かないとフェアではなかろう。
それはともかく、記者会見で大事なのは、どう質問したか、現場の国民の疑問を代わりに当事者にぶつけられたかどうか、である。質問者の日常の思想や行動は関係ない。
フォーサイスの言葉を借りるなら、「報道機関の使命はエスタブリッシュメントに釈明させることにある」からだ。
◇
ここまで書いた4月25日夜、今村復興相は自民党二階派パーティーで、震災の被害額に触れ「これがまだ東北で、あっちの方だったから良かった」と発言。更迭となった。2度目の失言ともなると安倍首相も放置できなかった。被災者に冷たい本音を最初に引き出した4日の質問の意味は大きい。新聞記者でなかったことは残念で仕方ない。
更迭に関連して二階俊博自民党幹事長は26日「マスコミは余すところなく記録を取り、一行でも悪いところがあれば、首を取れと。なんということか」「そんな人は、はじめから排除して入れないようにしないといけない」と述べた。
同日「国境なき記者団」(本部パリ)が発表した2017年の世界各国の報道自由度ランキングで日本は72位。さらに下げることをさせてはならない。
(了)

「ジャーナリストは絶対にエスタブリッシュメント(支配階層)の一員になるべきではない」「当事者の仲間になってはいけない。アウトサイダーでいなければならない」と、「はじめに」にある。今年79歳になる先輩ジャーナリストからの忠告の書とも読むことが出来る。
とはいえ、小説同様、軽妙な語り口で痛快だ。17歳で英国空軍に入隊、19歳でパイロット記章を手にし、5カ国語を流暢に操って取材、など快男児のエピソードは読みだしたら止まらない。楽しくページをめくっている時、痛快ではない、記者と当事者をめぐる事件が霞が関で起きた。
4月4日、今村雅弘復興相は記者会見で、東京電力福島第1原発事故に伴う自主避難者への対応を巡り、国の責任を質問したフリーの記者に「出ていきなさい。もう2度と来ないでください」「うるさい」と述べた。
この会見の詳報を読むと、記者への暴言の前に、自主避難者は「本人の判断」「本人の責任」であって、不服なら「裁判でも何でもやれば良い」と、被災者の気持ちに立って考えれば、冷たい発言を復興担当なのにしている。こちらがニュースだった。
しかし、5日の紙面は、共同通信原稿を使った加盟各社と毎日、日経、産経は、記者に対する暴言のみを報道した。読売は、一切記事にしなかった。
一方で朝日は「本人の責任」と述べたことをニュースにし、河北新報も独自の記事で自己責任を見出しに取った。
野党の批判もあり、共同通信は5日、復興相の言動が波紋を広げている、との大型解説記事を会見詳報も付けて流した。東京葛飾区に住む自主避難者の「大臣は汚染の状況を本当に知っているのか」など怒りの談話、福島県が3月末で打ち切った住宅無償提供の対象者が1万524世帯(昨年10月末時点)もいること、復興庁幹部にも「『本人の責任』という発言は、きつい言い方だった」との見解があることに触れた。
6日朝刊で加盟各紙が盛大に使った。地元の福島民友はじめ、秋田魁、中国などが2面などで、新潟日報が第2社会面、京都が社会面で、トップで扱い、東京は、霞ヶ関で開かれた、発言に抗議する集会を1面頭で使い共同記事のさわりを付けた。
信毎は共同記事を3面頭にするとともに、長野県内に自主避難している福島県民を取材し「国は早く避難者を福島に戻し、事故の幕引きを図りたいのだろう。見捨てられるのは悔しい」などの声を3段見出しで付けた。
朝日も第2社会面トップで、「切り捨てたい国の本音」と自主避難者の声をまとめた。
朝日、毎日、北海道、中日、信毎などが社説でも問題にした。復興相は6日、発言を事実上撤回、陳謝した。8日福島を視察した安倍首相が「私からもお詫びしたい」と発言、福島民友、福島民報が2面で大きく取り上げた。
気になるのは、新聞や放送の記者たちが、復興相の「2度と来るな」の発言に、後でどう対応したかだが、紙面では分からない。フリーの記者であっても、記者クラブがあれば抗議すべきところだ。質問内容次第で、記者が閉め出されることになれば、いずれは新聞、放送記者も自由に質問できなくなるからだ。
4日の会見を、かなり細かく記事にしている日本新聞協会の11日付「新聞協会報」によると「復興庁は記者クラブがなく、会見は庁側が運営する」という。なおさら、歯止めが必要で、そうでないと、官庁が気に入る記者のみの会見となり、国民の目がふさがれるのに等しい。
現場で解決できなければ、同協会編集委員会にまで持ち上げる手もある。
一連の報道で、違和感がしたのは、産経の7日5面。復興相が衆院東日本復興特別委で謝罪した記事のわき、「政論」という署名記事だ。「非生産的“逆上狙い”の挑発質問」と3段見出し。暴言のきっかけになった質問は、フリーの記者のたたみかける質問で復興相が感情的になり、暴言につながったとし、「まさに術中にはまったわけだ」と、暴言を引き出す狙いで質問が行われたかのように記述。記者のツイッターまで調べ「安倍晋三政権に批判的な姿勢が目立つ」とし、「『ためにする質疑』は生産的ではない」と結んでいる。
記者会見を生産的か非生産的か、で考えること自体、おかしいが、この筆者が自分は安倍政権にどういう姿勢なのかも書かないとフェアではなかろう。
それはともかく、記者会見で大事なのは、どう質問したか、現場の国民の疑問を代わりに当事者にぶつけられたかどうか、である。質問者の日常の思想や行動は関係ない。
フォーサイスの言葉を借りるなら、「報道機関の使命はエスタブリッシュメントに釈明させることにある」からだ。
◇
ここまで書いた4月25日夜、今村復興相は自民党二階派パーティーで、震災の被害額に触れ「これがまだ東北で、あっちの方だったから良かった」と発言。更迭となった。2度目の失言ともなると安倍首相も放置できなかった。被災者に冷たい本音を最初に引き出した4日の質問の意味は大きい。新聞記者でなかったことは残念で仕方ない。
更迭に関連して二階俊博自民党幹事長は26日「マスコミは余すところなく記録を取り、一行でも悪いところがあれば、首を取れと。なんということか」「そんな人は、はじめから排除して入れないようにしないといけない」と述べた。
同日「国境なき記者団」(本部パリ)が発表した2017年の世界各国の報道自由度ランキングで日本は72位。さらに下げることをさせてはならない。
(了)

2017/06/18
アガサ・クリスティはじめ推理小説作家が英国に多いのは、ジャーナリズムが早く発達したからだと、日経文化面で読んだ。私が好きなピーター・ラヴゼイ、ロバート・ゴダード、フレデリック・フォーサイスも英国だ。そのフォーサイスは昨年末、自伝とも言える「アウトサイダー」を出版した。最近読んだ本の中では「蜜蜂と遠雷」(恩田陸)と並ぶほど面白い。15歳で大学進学資格試験に合格、19歳でパイロット資格を得、5カ国語を使って世界を股にかける快男児の話は痛快です。
一方で、「ジャッカルの日」を書いて作家になる前、地方紙イースタン・デイリー・プレスの記者、ロイター通信の特派員、BBC放送局の記者を勤めており、ジャーナリスト魂を感じさせるくだりも少なくない。76歳の大先輩の言葉を、若い記者たちにも知ってもらいたい。さわりを転載します。
「(ジャーナリストに必要不可欠な資質は)あくなき好奇心と徹底的な懐疑的態度だ。何かの理由など別に知りたくないというジャーナリストや、人の話をなんでも鵜呑みにするジャーナリストがいるとしたら、それは無能なジャーナリストだ」(11㌻)
「ジャーナリストは絶対に支配階層(エスタブリッシュメント)の一員になるべきでない。誘惑がどれほど強くてもだ。われわれの仕事は権力を監視することであり、そこに加わるべきでない」(同)
「けっして当事者の仲間になってはいけない。アウトサイダーでいなければならないのだ」(12㌻)
「全国紙や通信社の記者は読者と顔を合わせない。だが地方紙では、窓の外に読者たちがいる。社屋に入ってきて、記事に誤りがあると抗議したりする。だから要求される水準が高いのだ」(108㌻)
「報道機関の使命はエスタブリッシュメントに釈明させることにある。絶対にエスタブリッシュメントの一部になってはいけない」(172㌻)
「外国特派員が肝に銘じておかなければならない鉄則がある。外務省の言うことを鵜呑みにするな、現地に長年すんでいる人に話を聞きに行け、という鉄則だ」(188㌻)
「一読者としてのわたしは不快なほどのうるさ型だ。ほかの作家の作品を読んでいると、どうしてもこう考えてしまうのである。この人は本当に現地を見たのだろうかと。(中略)どんな場所も、話しに聞くのと実際に見るのとでは大違いということがある。(中略)自分で行くのが不可能なら、次善の策として、その場所にいたことのある人から話を聞くべきだ」(360㌻)

一方で、「ジャッカルの日」を書いて作家になる前、地方紙イースタン・デイリー・プレスの記者、ロイター通信の特派員、BBC放送局の記者を勤めており、ジャーナリスト魂を感じさせるくだりも少なくない。76歳の大先輩の言葉を、若い記者たちにも知ってもらいたい。さわりを転載します。
「(ジャーナリストに必要不可欠な資質は)あくなき好奇心と徹底的な懐疑的態度だ。何かの理由など別に知りたくないというジャーナリストや、人の話をなんでも鵜呑みにするジャーナリストがいるとしたら、それは無能なジャーナリストだ」(11㌻)
「ジャーナリストは絶対に支配階層(エスタブリッシュメント)の一員になるべきでない。誘惑がどれほど強くてもだ。われわれの仕事は権力を監視することであり、そこに加わるべきでない」(同)
「けっして当事者の仲間になってはいけない。アウトサイダーでいなければならないのだ」(12㌻)
「全国紙や通信社の記者は読者と顔を合わせない。だが地方紙では、窓の外に読者たちがいる。社屋に入ってきて、記事に誤りがあると抗議したりする。だから要求される水準が高いのだ」(108㌻)
「報道機関の使命はエスタブリッシュメントに釈明させることにある。絶対にエスタブリッシュメントの一部になってはいけない」(172㌻)
「外国特派員が肝に銘じておかなければならない鉄則がある。外務省の言うことを鵜呑みにするな、現地に長年すんでいる人に話を聞きに行け、という鉄則だ」(188㌻)
「一読者としてのわたしは不快なほどのうるさ型だ。ほかの作家の作品を読んでいると、どうしてもこう考えてしまうのである。この人は本当に現地を見たのだろうかと。(中略)どんな場所も、話しに聞くのと実際に見るのとでは大違いということがある。(中略)自分で行くのが不可能なら、次善の策として、その場所にいたことのある人から話を聞くべきだ」(360㌻)

2017/06/04
何度も来日され、お目にかかったこともある環境活動家・思想家レスターR・ブラウン氏(米国)は、環境破壊の現状を「第3次世界大戦が始まっている。今の世代による未来の世代に対する戦争だ」と述べられていました。パリ協定離脱を表明したトランプは、この戦争をますます悪化させるのでしょうか。